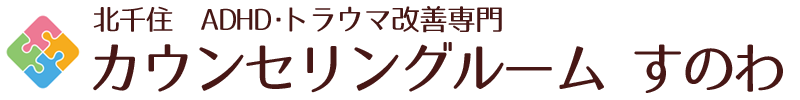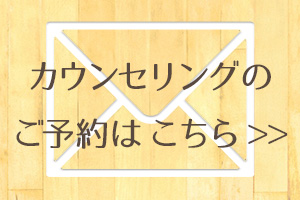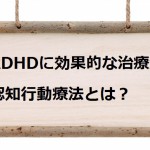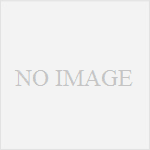【ADHD治療の未来】AIが変える!10年後・20年後・30年後・40年後のADHD支援と社会の姿
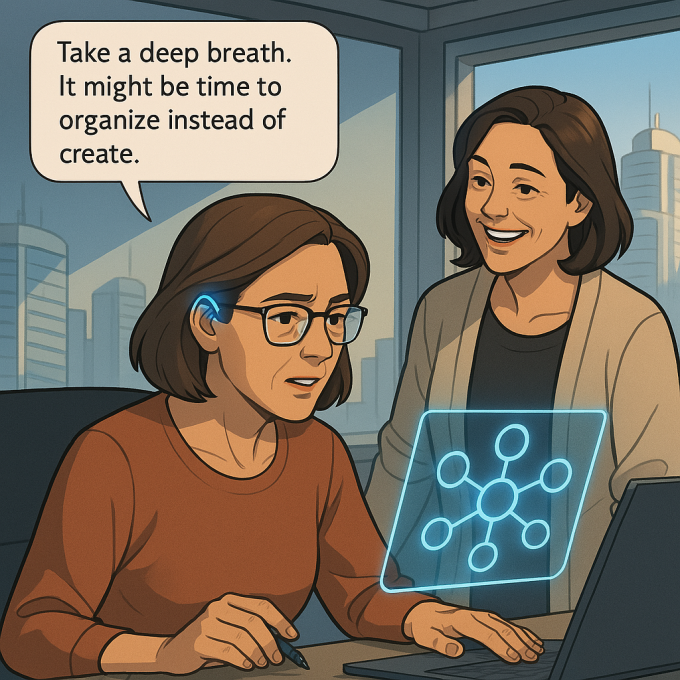
こんにちは!
足立区北千住カウンセリングルーム「すのわ」の臨床心理士・公認心理師の南和行です。
皆さん、**AI(人工知能)**を日常で活用していますか?
私は日々のカウンセリングや生活の中でも、AIを積極的に取り入れるようになってきました。
特にAIの「予測する力(推論)」は、**ADHD(注意欠如・多動症)**の支援においても大きな可能性を秘めています。
今回は、そんなAIに**「ADHD支援の未来予想図」**を描いてもらいました。
少し先の未来を想像しながら、「AI×発達支援」でできること、社会がどう変化していくかを物語形式でご紹介します。
ADHD治療とAIの未来、もしも今から数十年後、AIがもっと私たちの生活に寄り添ってくれたら──
そんな未来の“あるかもしれない物語”を描いてくれました。
ちょっとしたSFだけど、技術や社会の流れを見ていると、あながち夢物語でもないかもしれません。
4つの未来ストーリー、ぜひご覧ください
✅この記事はこんな方におすすめ
-
ADHDの診断や支援に関心がある方
-
発達障害とテクノロジーの関係に興味がある方
-
AIの医療・教育分野での活用に関心がある方
-
子どもの発達や未来の教育に関心がある親御さん・支援者の方
🌱2035年:「カズトのコーチ」~子どもを見守るAIコーチ〜
登場人物:カズト(12歳)、母、AIコーチ「リタ」
「カズトー、また忘れてる!歯医者、今日だよ!」
ランドセルを背負いながら家を飛び出したカズトは、母の声を背に振り返りもせずに走った。彼はADHDの診断を2年前に受け、今はAIコーチ「リタ」に支えられている。
「カズト、あと5分で英語。教室に着いたら、前から3番目の席に座ってみよう。今日は集中しやすい日だよ。」
スマートイヤホンから優しい声が響く。リタは彼の行動ログと感情の記録から、最適なサポートをしてくれる。授業中、リタは静かに息のリズムをガイドし、彼が気を散らしそうになると軽く通知を送る。
放課後、カズトはタブレットで「集中力トレーニングゲーム」を起動した。ゲームは医師から処方された“デジタル治療薬”だ。楽しい中にも認知機能の訓練が組み込まれている。
母は時々、アプリで息子の様子を見守る。以前は「また忘れてる」と怒ってばかりだったが、今では「今日は頑張ったね」と笑いかけられるようになった。
社会では、リタのようなAIが家庭や学校に導入され、「困りごとは工夫でサポートするもの」という文化が育ち始めていた。
🌿2045年:「アキラの選択」〜働きながら自分に合った支援を受けられる社会〜
登場人物:アキラ(30歳)、上司、AI支援デバイス「ニューロ・バンド」
アキラは企画書の締切を1週間先延ばしにしていた。学生時代からずっと「忘れっぽい」「集中できない」と言われてきたが、就職しても困りごとは続いていた。
けれど2040年の今、「困ってます」と言える社会になっている。
彼は上司に「最近ちょっと抜けてて…」と伝えた。上司は、「じゃあ、ニューロ・バンド、試してみたら?」と自然に勧めてきた。会社の制度で、脳波と心拍を感知して、注意力が下がると軽い刺激を送ってくれるウェアラブルデバイスが無償で利用できる。
その日の午後、アキラはデバイスを装着して仕事を始めた。集中が乱れ始めると、こめかみに微かな振動が伝わる。「あ、今注意散漫になってる」と自分を取り戻せる。
週末にはデジタルカウンセラーと1on1セッション。AIが生活習慣や作業効率を分析し、月曜からの提案をくれる。
「アキラさんは“深夜型&報酬型”の傾向が強いです。午前は単純作業に集中して、午後にクリエイティブ業務を配置しましょう。」
昔は「自分はダメだ」と思っていた。でも今は「自分に合うやり方がある」と知っている。社会が、それを一緒に探してくれる時代になった。
🌸2055年:「ナナミの未来」〜個性を生かす教育と家庭のかたち〜
登場人物:ナナミ(8歳)、担任の先生、祖母、ナナミの“脳アシスタント”
ナナミは、他の子とちょっと違うスピードで動く。教室で突然立ち上がって走り出すこともあった。けれど、誰も彼女を怒らない。
「ナナミちゃん、そろそろ休憩しよっか」
担任の先生がそう声をかけると、ナナミはニコッと笑って自分のスペースへ戻る。
ナナミの“脳アシスタント”は、軽く耳につけるだけの装置。彼女の脳の動きを読み取って、「そろそろ休憩」「いま集中できてる」などを静かに伝えてくれる。
祖母は最初この技術に戸惑った。でも、今は「ナナミの個性が花開く道具」だと感じている。
「昔は“落ち着きがない”って言われて、学校で怒られてばかりだったのよ。今は、先生もクラスも、それを“好奇心”として受け止めてくれる。」
ナナミは、週に一度「わたしの脳の使い方ノート」を書いている。AIと一緒に、自分のやりやすい工夫を見つけて、未来の自分に手紙を出す。
「わたしの脳はね、ちょっと飛び跳ねるウサギみたい。でも、いいところもたくさんあるんだよ。」
2050年の社会では、ADHDという言葉は少しずつ使われなくなっていた。
“違い”は“個性”に、“困りごと”は“工夫するチャンス”に。
そしてナナミは、自分らしい未来を生きていく。
🌏2065年:「ミナ、46歳、そして今」〜脳の多様性が強みになる社会へ〜
登場人物:ミナ(46歳・グラフィックデザイナー)、パートナーのリエ、脳インターフェース「マナ」
ミナは、ADHDの診断を受けたのは33歳のときだった。
子どもの頃は「変わってる子」、大人になってからは「仕事ができない人」と言われ続けてきた。
でもそれは、彼女の“思考の速さ”や“同時に5つのことを感じ取れる力”を、誰も言語化できなかっただけだった。
2060年、ミナはデザインスタジオのチーフをしている。
彼女のこめかみには、「マナ」という小さなニューロチップが埋め込まれている。
マナは彼女の注意や感情のパターンをリアルタイムで理解し、負荷がかかりすぎると、そっと光る。
「ミナ、深呼吸。今は“創造”じゃなく“整理”の時間かも。」
ミナはそれを合図に作業スタイルを変える。思考を音声でアウトプットし、それをマナが自動でマインドマップ化してくれるのだ。
昔の自分なら、「ごちゃごちゃしててダメだ」と責めていた。でも今は、「私はこういう脳なんだ」と受け止め、パートナーのリエとも共有している。
リエは笑って言う。
「ミナがいきなり3案同時に話し出すの、前はびっくりしたけど、今はすごく面白いって思えるよ。」
社会も変わった。
求人票には「神経多様性フレンドリー」と書かれ、企業は脳特性に合わせた働き方の調整が標準化された。
通勤・在宅・バーチャル・メタバース…自分の集中しやすい環境を選べることが“当たり前”になっていた。
週末、ミナは近所の図書館で、子どもたちに「わたしの脳の取扱説明書」を描くワークショップを開いている。
「うまくいかないこともあるけど、それは“工夫のチャンス”なんだよ。脳って、一人ひとり、みんな違うんだ。」
ミナの声に、子どもたちはうなずいた。
自分を知る。受け入れる。そして、未来をつくる。
2060年のミナは、「変わってるね」と言われることを、誇らしく思っていた。
🔚まとめ:AIとともに歩むADHD支援のこれから
いかがでしたか?
AIとADHD治療の未来は、決してSFだけの話ではありません。
すでに現在の技術でも「AIによるスケジュール支援」「感情ログ」「注意リマインダー」「デジタル療法」など、実用化が進んでいます。
これからの時代は、
「困りごと=ダメなこと」ではなく、
「困りごと=工夫のチャンス」と捉え、誰もが自分らしく生きられる社会を目指す時代です。
AIの進化 × 人のやさしさと理解
この両方がそろってこそ、本当の意味での“神経多様性フレンドリー”な未来が実現していくのだと思います。
そして、このAIを使ったサポートは既にこの2025年の現在も活用することはできます。
AI活用に興味をもってくれた方は、こちらの講座がおすすめです。
📢【関連講座のご案内】AIを使ってADHDの悩みを解決したいあなたへ
やらなきゃいけないのに動けない…その悩み、AIなら5秒で解決!
\AI初心者でも安心!/ ADHD特化型ChatGPT活用法セミナー 開催中
・ADHDの特性に合わせたAI活用法
・ChatGPTでできる時間管理やタスク分解のコツ
・実際の支援現場やセルフケアへの応用方法も紹介
=やらなきゃいけないのに動けない…その悩み、AIなら5秒で解決!= AI初心者OK! ADHD特化型ChatGPT活用法セミナー
https://peatix.com/event/4346166/view